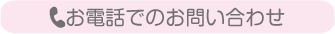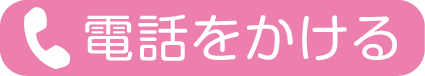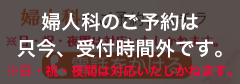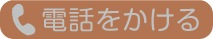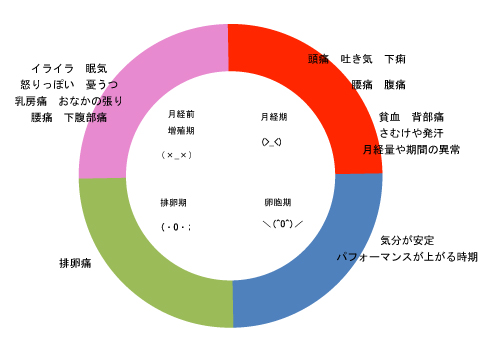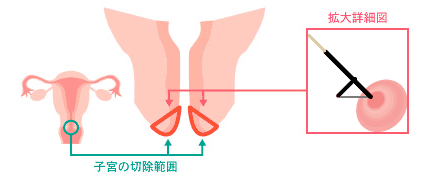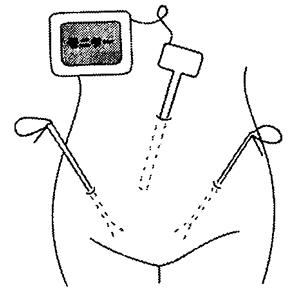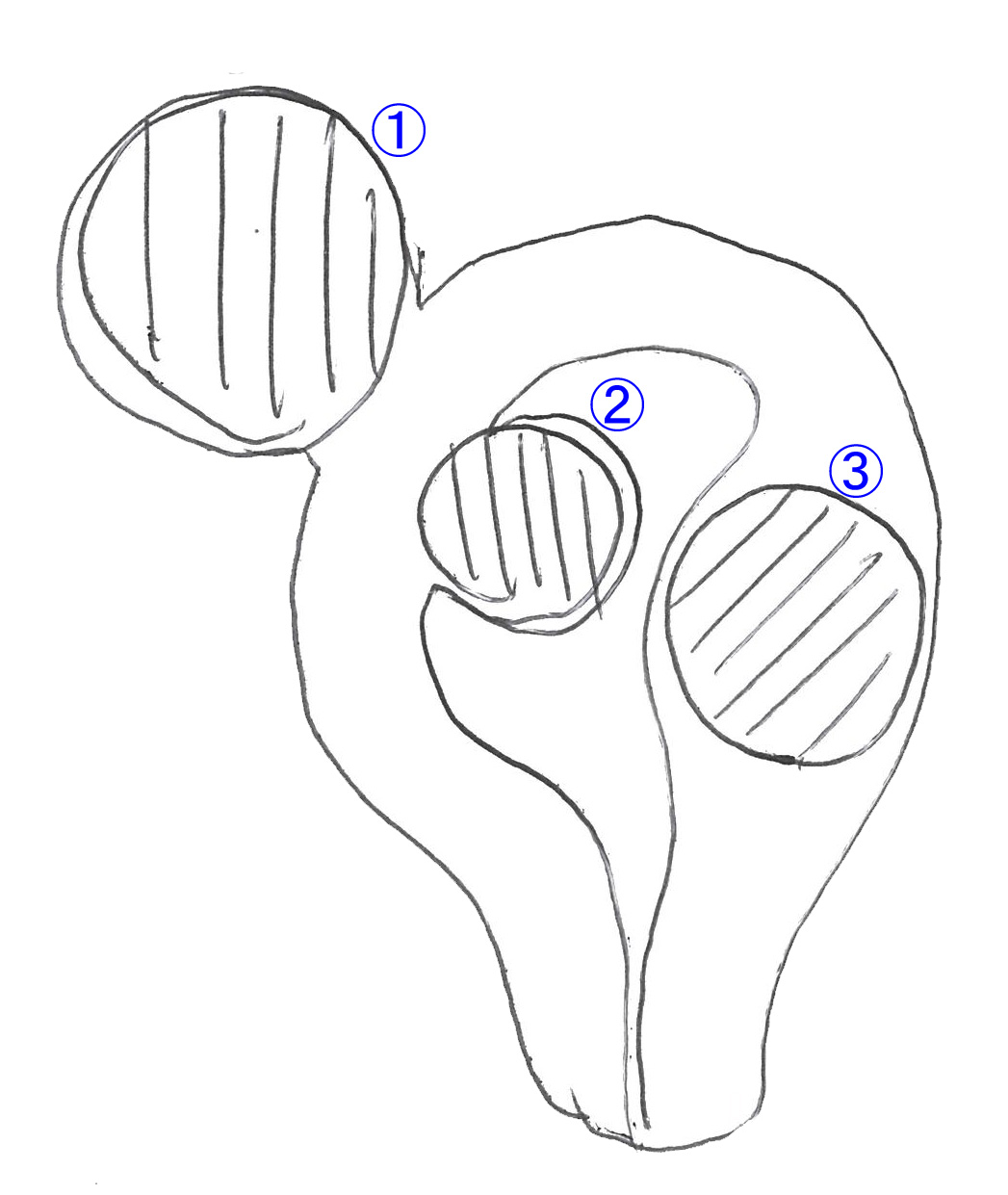性器クラミジア感染症
クラミジアという細菌が原因で起こる日本で最も多い性感染症です。
主に性交渉やオーラルセックスによって、子宮頚管や骨盤内、咽頭に感染します。
症状は、黄色い帯下が少量出る程度か無症状のことが多いので、感染に気づかない場合も多くあります。進行すると下腹痛や発熱することもあります。
クラミジア感染症を無治療で放置すると、卵管に障害を起こし卵管性不妊症の原因になったり、卵管妊娠(子宮外妊娠)の原因になることがあります。
また妊娠中は産道感染により新生児の肺炎や結膜炎を引き起こします。
診断は、現在の感染状況については子宮頚管から直接細胞を取る抗原検査を、過去の感染状況を知るには血液で抗体検査を行って診断します。
治療はクラミジアに有効な抗生物質の内服で通常除菌できますが、セクシャルパートナーが無治療の場合、性行為によって再感染しますのでパートナーとの同時治療が必要です。
クラミジアは、自覚症状に乏しく感染に気づきにくい性感染症ですので予防が重要です。
コンドームの適切な使用は有効な予防法です。ただし、オーラルセックスの時も使用する必要があります。
淋菌感染症
淋菌を原因菌とする性感染症です。クラミジアと同様にあらゆる性行為で感染します。
症状は男性では尿道炎の症状が強く出ますが、女性では症状が無いか軽いことがほとんどです。クラミジア同様、オーラルセックスによって咽頭にも感染します。
淋病も不妊の原因になったり、産道感染により新生児結膜炎を引き起こす可能性があります。
診断はクラミジアと同様に子宮頚管分泌物を採取して行います。クラミジアと同時検査が出来ますので、当院では帯下異常で来られた方には一般細菌検査とクラミジア、淋菌同時検査をするようにしています。
治療は抗生物質の点滴で行います。コンドームの適切な使用が有効な予防法です。
膣トリコモナス症
トリコモナスは性行為を介してトリコモナス原虫に感染することで発症します。
症状がある場合は、帯下の悪臭、泡状の帯下が出るなどが多いですが、自覚症状が無い場合も多くあります。診断は膣分泌物の培養検査によって行います。
治療は洗浄+膣錠を数回行い、同時に抗菌薬の服用で行い、パートナーも内服薬の服用で同時に治療します。
トリコモナス膣症もコンドームの使用で予防可能です。
性器ヘルペス
性器ヘルペスは主に性行為によって、ヘルペスウィルスに感染することによって発症します。
性器ヘルペスの症状としては、性器周辺に見られる水ぶくれや潰瘍などが典型的な症状です。
熱が出たり、足の付け根のリンパ節が腫れることもあります。ひどい時は痛みのため排尿も困難になるほどの痛みを伴います。
初めて感染してからすぐに症状が出る場合もありますが、感染してもしばらく症状が出ない場合もあります。診断は病変部から直接細胞を取って、ヘルペスウィルスの抗原を検出します。
治療は通常、抗ウィルス薬の経口薬と軟膏が処方されます。重症化したときは抗ウィルス薬の点滴が必要なこともあります。
ヘルペスの特徴として再発を繰り返すという点があります。抗ウィルス薬は症状を早く和らげてくれる効果はありますが、ウィルスを死滅させることは出来ないからです。
病変が消失した後は、ヘルペスウィルスは神経に潜伏し、体が弱っている時や精神的なストレスがあるとウィルスが活性化されて再発すると考えられています。
ただ再発の時は、初めて症状が出たときに比べて軽症のことがほとんどです。
また妊娠中に性器ヘルペスを発症した時も注意が必要です。妊娠の時期により対応はことなりますが、出産直前に性器周辺に病変を認める場合は、産道感染による新生児ヘルペスを発症する可能性があるためです。新生児ヘルペス感染症は死亡率が高く、神経学的後遺症を残す恐れのある病気です。
そのため帝王切開術が必要になることがあります。
尖圭コンジローマ
尖圭コンジローマも性感染症の一つで、性器や肛門周辺にとさかの様なとか、カリフラワー状のとか表される特徴的なイボが出来ます。
痛みやかゆみなどの自覚症状はあまりありません。
尖圭コンジローマは、ヒトパピローマウィルス(HPV)というウィルスを病原体としています。
ヒトパピローマウィルスには多くの種類があり、良性のものはコンジローマに、悪性のものは子宮頸がんの原因にもなります。診断は肉眼的に比較的容易につきます。
治療は、ベセルナクリームという塗り薬による薬物療法と電気メスでイボを切り取る手術療法があります。
梅毒
主に性行為によって梅毒トレポネーマという病原体に感染することによって発症します。
梅毒は比較的まれな疾患となっていましたが、近年世界的に感染者が増えており、日本でも若い女性を中心に感染者が急増しており、一般の人たちの普通の性的活動の中で感染する性感染症となっています。
初期症状としては性器に硬いしこりが出来たり、足の付け根のリンパ節が腫れたり、体に発疹がたくさん出たりなどがありますが、自分では気づかない程度のこともあります。
感染に気づかずに治療しないままでいると徐々に進行していきます。
また梅毒に感染したまま妊娠すると、胎盤を通じて病原体が胎児に移ってしまい、梅毒を持った赤ちゃんが産まれてくる恐れがあります。これを先天性梅毒と呼びます。
病原体は皮膚や粘膜の小さな傷から侵入するため、コンドームである程度予防できますが完全ではありません。
梅毒の確定診断は血液検査で抗体を検出することによって行います。
治療はペニシリンを数週間内服することにより完治させる事ができます。
HIV 感染症(エイズ)
HIV(ヒト免疫不全ウィルス)とは、ヒトの体を様々な細菌やウィルスなどの病原体から守る免疫細胞に感染するウィルスのことです。HIV が免疫をつかさどる細胞に感染すると、これらの細胞の中でHIV が増殖して免疫機能が働かなくなり、普段は感染しない病原体にも感染しやすくなって、様々な病気を発症します。
この病気の状態をエイズ(後天性免疫不全症候群)といいます。
HIV に感染すると、HIV は精液、膣分泌液、血液、母乳などに多く含まれるようになるため、感染は性行為による感染、針刺し事故や輸血などの血液を介した感染、母子感染に分けられます。
日本で1980 年代に、HIV 感染者の血液から作られた血液製剤を使用したことによる多数のHIV 感染者を生み出した薬害エイズ事件がおきましたが、現在は性行為による感染が最も多いとされています。
診断は血液で抗体検査を行いますが、感染機会があってからHIV が陽性に出るまでには約1ヶ月かかります。
治療法は抗HIV 薬を服用することによって行います。エイズはかつては死の病と呼ばれたこともある病気ですが、現在は薬が劇的に進歩しており、エイズ発症前から薬を長期服用し続けることにより、非感染者と変わらない寿命を全うすることが出来るようになりました。そのため早期発見、早期治療開始が重要となります。